もやしは、スーパーやコンビニはもちろんのこと、薬局の冷蔵コーナーにも置かれていたりする、身近な野菜です。
クセのない味は他の食材の邪魔にならず、またシャキシャキ食感は料理によいアクセントを与えてくれます。
私も普段からカサ増し野菜として重宝していますが、もやしのことを日に当てずに育てた脇役としか思っていませんでした。
もやしって、栄養あるのかな・・・?
ふと、好きなわりには何も知らないことに気づき、毎日お世話になっている【もやし】のことを調べてみることにしました。
この記事を読み終えるころには、もやしについての理解が深まり、もやし愛もさらに大きくなっていることでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
もやしはおもに3種類
- 緑豆もやし
- 黒豆もやし
- 大豆もやし
他にも「もやし」として、アルファルファ、ソバもやし、また大麦もやし(麦芽)などがあります。
ここでは一般に流通している、緑豆もやしについて取り上げます。
以下もやしと記述しているのは、全て緑豆もやしのことをさします。
もやしの選び方
◎色白でパリッと固いものを選ぶ
× 水が出ているものは避ける
× 茶色に変色しているものは避け
冷蔵での日持ち
冷蔵庫で2~3日(袋に書かれている消費期限を守りましょう)。
冷凍での日持ち
冷凍した場合は約2~3週間が目安。
冷凍の方法
- 未開封なら袋のまま冷凍可
- 開封した場合はもやしを流水で洗い、水けを切り、使う分量ごとに小分けにして、冷凍用ジップロック入れて冷凍庫へ。
- 加熱した場合は、粗熱をとってから、使う分量ごとに分けて小分けにして、冷凍用ジップロックに入れて冷凍庫に保存。
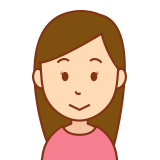
開封したり加熱した場合は冷凍前の工程が増えるので、
未開封のまま袋ごと冷凍することをおすすめします!
(まぁ私は横着したいので、開封しても袋を閉じてそのまま
冷凍庫にいれていますが。ボソッ)
冷凍もやしは解凍しない
冷凍もやしは解凍せずそのまま鍋やフライパンに入れて調理可です。
ただし、加熱してから冷凍したものは、クタッとした食感になるのでスープなどの汁物に使うとよいでしょう。
傷んでいるサイン
× 水気やぬめりが出ている
× 茶色く変色している
× 酸っぱいような臭いがする
⇩
そうなったら、残念ですが廃棄しましょう。
※私自身、うっかり変色させてしまったもやしをもったいなくて捨てられず、、、。
よく洗って長めに加熱し食べたことがあります。
その後お腹をこわすこともなかったですが、味や栄養の面から人にはおすすめいたしません。
洗う必要なし
もやしは出荷する前にきれいな水で洗ってあるので、調理前に洗う必要はありません。
生で食べられるか
加熱調理を前提として生産されているので、生食は推奨されていません。
特に幼児、高齢者、免疫不全者の方は加熱して召し上がることをおすすめします。
レンジ調理
レンジ600Wでもやし100gで1分が目安です。
(たいていの市販もやしは一袋200gなので2分ほど。一袋250gなら2分半)
「袋ごと電子レンジ調理可」と書かれていなければ、袋からもやしを出して耐熱皿に広げ、軽くラップをかぶせてレンジにかけましょう。
シャキシャキ感を残す調理のコツ
水ともやしを入れて火にかけ、沸騰したらすぐにもやしをザルにあける。
ザルにあけたあとは、水にさらすと水っぽくなるので、水にさらさない。
農薬は使っているか
もやしは衛生管理された工場で水耕栽培されているので、農薬は使いません。
もやしの旬
人工栽培されている野菜なので、一年を通して旬です。
生産量全国一位は
栃木県がもやしの生産量トップです(2024年)
もやしの栄養
もやしは95%は水分です。
100gあたり15kcalと低カロリーなので、ダイエット中の方にもおすすめです。
食事前に先に茹でもやしを食べておけば血糖値の急激な上昇をおさえ、食べへぎを防ぐ効果も期待できます。
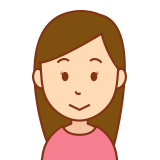
安価なので続けやすいです
たんぱく質も100gあたり1.8g含まれているので、1袋200gだと3.6gのたんぱく質がとれることになります。
その他にも、もやしにはビタミン、ミネラル、たんぱく質、食物せんいや必須アミノ酸など、多くの栄養が含まれているヘルシー食材なのです。
<生の緑豆もやし100gあたり>
◆15Kcal
◆炭水化物 2.4g
◆たんぱく質 1.8g
◆食物せんい 1.3g
◆カルシウム 9mg
◆ビタミンC 7mg
◆ビタミンB1 0.04mg
◆ビタミンB2 0.05mg
◆カリウム 79mg
◆鉄 0.2mg
◆コレステロールゼロ
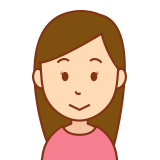
・たんぱく質はにんじん🥕の2.5倍
・カルシウムはりんご🍎の3倍
・食物せんいはトマト🍅の1.3倍
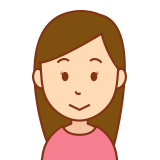
もやしは発芽野菜なので、
未知の栄養素があるかも
しれませんね。
まとめ
もやしは、冷凍で長期間保存できたり、加熱時間によって好みの食感にしたりと、取り扱いのコツを知ることで、より美味しくより便利に使うことができます。
カロリーを心配することなくモリモリ食べられる、お助け食材のもやし。
ぜひ毎日の食卓に取り入れて健康にお役立て下さい。
参考資料:
もやし生産者協会
文部科学省 | 食品成分データベース
内閣府 | 食品安全関係情報詳細


